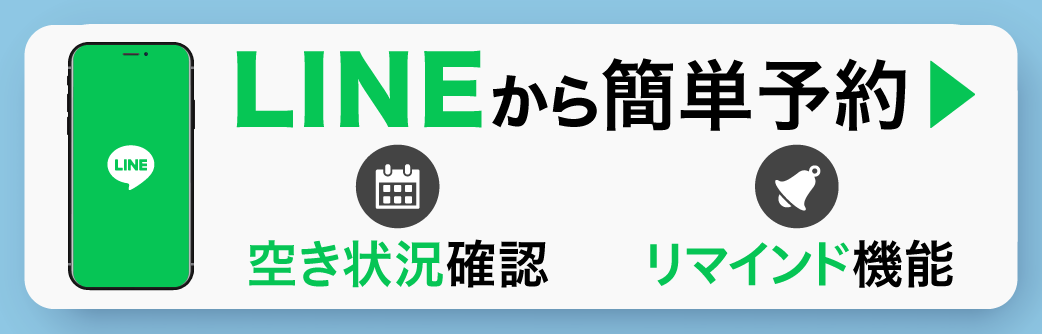根管治療指導医による治療
(自由診療)
当院の根管治療担当医
Watanabe Hiroaki
渡邉 浩章
経歴
東京歯科大学卒業
東京歯科大学大学院歯学研究科卒業
所属学会
日本歯内療法学会 指導医
日本歯科保存学会 認定医
American association of endodontics 会員
日本歯科理工学会 会員
日本接着歯学会 会員
[wp_title]
(自由診療)
当院の根管治療担当医
Watanabe Hiroaki
東京歯科大学卒業
東京歯科大学大学院歯学研究科卒業
日本歯内療法学会 指導医
日本歯科保存学会 認定医
American association of endodontics 会員
日本歯科理工学会 会員
日本接着歯学会 会員

Hiroaki Watanabe, Kensuke Saito, Katsutoshi Kokubun, Hodaka Sasaki, Masao Yoshinari. Change in surface properties of zirconia and initial attachment of osteoblastlike cells with hydrophilic treatment. Dent Mater J. 2012; 31(5):806-14.
牛窪 敏博,渡邉 浩章.ニッケルチタンファイルへ連続回転運動あるいは反復運動を負荷時に生じる周期疲労破折特性.日本歯内療法学会雑誌.2016;37:150-155.
牛窪 敏博,渡邉 浩章.XP-endo Shaperによる楕円根管模型形成における切削量および非接触領域のマイクロCTによる評価.日本歯内療法学会雑誌.2017;38:159-164.
渡邉 浩章,牛窪 敏博.マルテンサイト相を有するニッケルチタンロータリーファイルの形状記憶能におけるオートクレーブの影響.日本歯内療法学会雑誌.2020;41:179-184.
骨内インプラントにおけるス クリューホール内の細菌叢(第129回 日本歯科保存学会秋季学術大会,2008.) 早期負荷骨内インプラント周囲骨形成のマイクロCTによる検討(第38回 日本口腔インプラント学会,2008.) 東京歯科大学千葉病院臨床研修歯科医に対する手術用顕微鏡教育の現状(第130回 日本歯科保存学会春季学術大会,2009.) 擬似体液(SBF)中におけるハイドロキシアパタイト被覆骨内インプラント表層の変化(第39回 日本口腔インプラント学会,2009.) 試作根管シーラーの生物学的検討(第131回 日本歯科保存学会秋季学術大会,2009.) 東京歯科大学千葉病院臨床研修歯科医に対する手術用顕微鏡教育の現状(第287回 東京歯科大学学会,2009.) レジン系根管充填用シーラーの細胞毒性(第288回 東京歯科大学学会,2009.) 根尖病巣に接して植立された骨内インプラントの臨床経過(第132回 日本歯科保存学会春季学術大会,2010.) 異なる MPCポリマー濃度によるMC3T3-T1の増殖に関する研究(第135回 日本歯科保存学会秋季学術大会,2011.) 骨芽細胞様細胞の初期接着・増殖に及ぼすジルコニア表面濡れ性の影響(第41回 日本口腔インプラント学会,2011.) コンビーム CT とマイクロスコープを用いた歯内歯の非外科的治療(第32回 日本歯内療法学会学術大会,2011.) 歯根尖切除術後の骨創腔の治癒における吸収性膜の影響(第137回 日本歯科保存学会秋季学術大会,2012.) 直接法または直接間接法で植立したポストの維持力(第33回日本歯内療法学会学術大会,2012.) 人工根管を用いた周期的疲労に対する K3XFとK3の比較(第138回 日本歯科保存学会春季学術大会,2013.) 3種の模擬根管を用いた各種ニッケルチタンファイルの繰り返し疲労の測定(第34回 日本歯内療法学会学術大会・第9回世界歯内療法会議,2013.) 新しい根管シーラーは根管系の封鎖性を改善したか?(第34回 日本歯内療法学会学術大会・第9回世界歯内療法会議,2013.) マルテンサイト相を有するニッケルチタンロータリーファイルの形状記憶能におけるオートクレーブの影響(第41回 日本歯内療法学会学術大会,2020.)
3種類の模擬根管を用いた各種Ni-Ti製ファイルの繰り返し疲労の測定
世界の歯内療法の潮流 第9回世界歯内療法会議の主な演題から
別冊 ザ・クインテッセンス YEARBOOK 2014,クインテッセンス出版,68-69,2014.
マテリアルを使いこなそう![5]シングルユースファイル
ザ・クインテッセンス,クインテッセンス出版,33;1121-1123,2014.
クラックトゥースへの対応
歯界展望,医歯薬出版,127;41-55,2016.
MTAは本当に魔法の薬か? ―水酸化カルシウムとの比較にみる生活歯髄療法での位置づけ―
31TOPICSで先取りする歯科臨床の羅針盤,
インターアクション,116-121, 2017.
MTAを用いたエンドの臨床 予知性の高いバイオセラミックマテリアルの応用法
Chapter6 永久歯の生活歯髄保存療法
医歯薬出版,54-63, 2018.
湾曲根管, あなたならどうする?
3. オーステナイト相のファイルとマルテンサイト相のファイルの特性
ザ・クインテッセンス,クインテッセンス出版,40;60-63. 2021.
マルテンサイト相を有するニッケルチタンファイルの特性について
別冊ザ・クインテッセンス 日本歯内療法学会がすべての歯科医師に贈る最新トレンド.
クインテッセンス出版,68-69. 2021.
根管充填材料 1 ーガッタパーチャと従来型シーラーの特性と問題点ー
ザ・クインテッセンス.クインテッセンス出版,41;1544-1550,2022.
解剖学的形態を維持した根管形成・拡大
効率的で効果的なNiTiロータリーファイルの臨床応用
医歯薬出版,114-146,2023.
日本歯内療法学会指導医の申請要件は、日本歯内療法学会に専門医*として5年以上在籍し研鑽を積む必要があります。
さらに、指定された研修を受講して日本歯内療法学会学術大会での発表・学会誌への論文発表ならびに指導医の推薦が必要になります。
学会の審議会での審査を受けて合格した場合に、日本歯内療法学会指導医としての資格が与えられます。
指導医資格は期間が決まっており、当然のことながら継続的な知識の習得が必要になります。更新は5年ごとに研修の証明を添えて、学会の審議会に申請する必要があります。
日本歯内療法学会指導医の申請要件は、日本歯内療法学会に専門医*として5年以上在籍し研鑽を積む必要があります。
さらに、指定された研修を受講して日本歯内療法学会学術大会での発表・学会誌への論文発表ならびに指導医の推薦が必要になります。
学会の審議会での審査を受けて合格した場合に、日本歯内療法学会指導医としての資格が与えられます。
指導医資格は期間が決まっており、当然のことながら継続的な知識の習得が必要になります。更新は5年ごとに研修の証明を添えて、学会の審議会に申請する必要があります。
「根管治療」とは、俗に言われる根っこの治療のことです。歯の神経の治療や歯の根っこの先にできた膿の袋に対する治療とも言われております。
一般的に、虫歯で大きな穴があいてしまった時に、
歯の神経を取らないといけない時や、以前に神経の治療をしたが根っこの先の部分に膿みの袋ができてしまい、もう一度治療をしなければならない時に行う
処置のことを指します。

しかし、歯の中の神経が入っている管である「根管」は、小さく狭い空間であるため、肉眼ではなかなか見えにくく処置が難しい場所です。
そこで、当院では「マイクロスコープ」と呼ばれる手術用実体顕微鏡を用いて術野を拡大し、この処置を行うようにしております。
当院では、「ラバーダム防湿」と呼ばれる方法を採用し、
治療時にゴム製の薄いシートを歯科用の金属製の留め具で歯に装着して治療を行います。
装着することに対して少し違和感を感じられる場合もありますが、
ラバーダム防湿を行うことにより、お口の中の細菌や
唾液が根管内に侵入するのを防いでくれます。
根管治療は、処置時間が長くなってしまい大変ですが、
歯科治療のなかでも重要な治療行為の1つです。
安全で予後の良い治療を少しでも短い時間で行えるように心がけております。
「何もしなくてもズキズキとした痛みがある。」
「冷たいものや温かいものが強くしみている。」
このような症状があると、神経を取る処置が必要になる可能性があります。
きちんとした検査を受けていただき、問題解決の方法を相談して頂くことをお勧めいたします。
また、以前に根管治療を受けた歯について、
「歯肉にニキビのようなものができたり腫れてきた」
「噛むと痛い」
「何もしていなくてもズキズキとした痛みがある。」
このような症状があると、根管治療の再介入が必要になる可能性があります。
この場合も、きちんとした検査を受けていただき、問題解決の方法を相談して頂くことをお勧めいたします。
ここでご紹介したケース以外にも根管治療が必要になる場合もございますので、何か気になることがありましたら担当医にご相談して頂くことをお勧めいたします。

「根管治療が必要になる場合は細菌感染が原因であるため、「無菌的な処置を行うこと」が大前提となります。
しかし、その基本的なルールを守らずに治療が行われている現状があります。
初めての根管治療の際、根管治療を専門とする歯科医師の治療を受けることで「再発および再治療のリスクを抑える」ことができる可能性があります。
しかし、根管治療は歯科治療のなかでも難易度が高い上、「無菌的な処置」などの考え方を守らない治療を行うことで治療後に症状が出て再治療を繰り返す可能性が高くなり、再介入により何度もやり直しの治療を受けておられる方もいらっしゃいます。
そのような度重なる治療によって、歯を削ることになり、結果として物理的な歯の量は減っていきます。最終的には咬む力に耐えられなくなってしまい、歯が割れてしまう原因にもなります。
この結果、最悪の場合は保存不可能と診断されて抜歯になるケースもあります。
歯科治療において、治療介入の機会をできる限り減らして健全な状態で歯を削らずに保存していくことが重要になります。それは根管治療においても同じことです。
基本的なルールを厳守して治療を行うことにより、再治療になってしまうリスクを減らすことができ、残存歯質を残した上で機能できるように使って頂くことが大切であると考えます。

根管治療は期間が長くなればなるほど根管内の感染リスクが増加し、予後の悪化に深く関わってきます。
マイクロスコープによる精密な根管治療中は、おロを開けて頂く時間が、一般的な治療に比べて、長くなってしまいやすく治療時間が大変かと思われます。
しかし、今後の歯の寿命や被せ物を被せた際の予知性に関わる、非常に重要な処置の治療工程の一つと考えているため、少しでもリラックスしていただきながら、できるだけ短い時間や期間で終えられるように配慮し、予知性の高い治療を心がけて処置を行っております。
不安や、ご不明な点などございましたら、是非、担当医や根管治療指導医にご相談ください。

当院では、マイクロスコープを使用して、精密根管治療を実地しています。
肉眼では見えない複雑な根管内を確認し、治療前には必要に応じて CT撮影を行って3次元的に評価して、
細かな診査・診断を行った上で、治療を進めて参ります。
そこで、当院の特徴を以下に列挙致します。
POINT1
マイクロスコープを用いることで、肉眼では見逃してしまうような小さな根管や微細な状況を可能な限り目視できるようになります。現在の根管治療においては、必須の機材の1つと考えられており、治療を行う上では必要不可欠であると考えております。
ただし、マイクロスコープは視覚強化の為の道具です。マイクロスコープを用いて治療することにより、治療の精度は向上するかもしれませんが、飛躍的に根管治療の成功率を上げるものではありません。
さらに、マイクロスコープを導入してもすぐに使えるものではなく、使用方法に慣れていないと治療に使うことはできません。
マイクロスコープを使用しての根管治療は、保険診療においても認められており普及してきています。
しかし、根本的にマイクロスコープを使用するだけで治療の成功率が上がるわけではなく、根管治療中の無菌的な処置への配慮や治療に対するコンセプトを厳守して治療を行うことで予知性の高い治療につながると考えております。

POINT2
マ管治療が必要になる原因は口の中に存在する細菌であることから、処置が必要な歯に細菌を近付けないもしくは持ち込まないように配慮する必要があります。
基本的に、ラバーダム防湿を行うことにより口の中と治療が必要な歯を隔離することができる為、根管内に唾液を介して細菌が侵入することを防ぐことができます。
原因となる細菌がいる環境と同じ空間で根管治療を行っても、予後は悪いです。よって、ラバーダム防湿は根管治療を行う上で絶対に必要なものであると考えています。
ラバーダム防湿は保険診療においても使用することができますが、使用されていない歯科医院が存在しているのも現状です。
どの様な治療をお受けになりたいかをお考え頂けますと幸いです。

POINT3
根管内は、根が曲がっている「彎曲(わんきょく)」や、木の枝のように分岐している「側枝(そくし)」、根の先端がくっついている「融合」など、非常に歯の外観だけでは想像できないような複雑な形態をしています。
従来から根管治療で使用される「ステンレス製ファイル」では、非常に硬くて直線的な作業しかできません。直線的な根管内には適応されますが、彎曲(わんきょく)などの複雑な根管内に対するアプローチには困難であり、複雑な根管内の細菌含めた汚れを物理的に清掃する作業には無理があり限界もございます。
「ニッケルチタン製ファイル」は、超弾性と形状記憶の性質を持っている器具です。複雑に彎曲(わんきょく)した根管であっても、できる限り根管の既存の形態に追従させることが可能となっており、治療時間の短縮が可能となります。
当院では、ファイルの特徴をふまえて「ステンレス製ファイル」と「ニッケルチタン製ファイル」を併用して治療を行っています。治療部位によってファイルを使い分け、最も効率的なものを選択して治療しています。
ニッケルチタン製ファイルに関しては、様々な大きさや形状のファイルが市販されていることから、状況に応じて使い分けております。
「このニッケルチタン製ファイルを使用したから成功率が飛躍的に向上する」というものは存在しません。ニッケルチタン製ファイルは、使い方を間違えると効率的な根管治療はできません。
さらに、根管治療を行う上でのコンセプトを遵守しない限り予知性の高い治療は望めません。

当院が行っている、治療の詳細について以下にご紹介します。

歯科用CT装置(以下CT)は従来の2次元的なデンタルエックス線写真でも大まかには判断することができますが、3次元的なCTを用いることで、デンタルエックス線写真では把握できないとされる微細な病変や、病変の大きさ、骨の厚み、神経の走行も画像化することで、3次元的に評価をして、治療に必要とされる情報を収集でき、より確定的な診断に導き、それに対しての治療法の選択が可能となります。
CTの結果を用いて精密な診査・診断を行うことにより治療部位をとり正確にし把握し、正確な治療を可能にしています。

歯科用CT装置(以下CT)は従来の2次元的なデンタルエックス線写真でも大まかには判断することができますが、3次元的なCTを用いることで、デンタルエックス線写真では把握できないとされる微細な病変や、病変の大きさ、骨の厚み、神経の走行も画像化することで、3次元的に評価をして、治療に必要とされる情報を収集でき、より確定的な診断に導き、それに対しての治療法の選択が可能となります。
CTの結果を用いて精密な診査・診断を行うことにより治療部位をとり正確にし把握し、正確な治療を可能にしています。

「根管充填」は、神経が入っていた空間をきれいに洗浄して形を整えた後に、ゴム状の材料を用いて、神経を取り除いたことにより生じた空洞を、緊密に塞いで詰める処置です。この際に、この空洞をしっかり緊密に塞ぐことができなければ、再び細菌に感染してしまいます。
一般的にゴム状の材料を用いて隙間を塞ぎますが、複雑な形態をしている根管内では緊密に塞ぎきれないケースがあります。充填方法には様々な種類や方法があり、治療している歯の形態や状態に必要に応じて、使い分けて行っております。

根管治療は基本的に国民健康保険で行える処置ですので、保険での治療も可能です。
保険診療には使用材料などのルールが決められております。
保険診療で決められた範囲内での治療を行うのか、もしくは保険診療の決められた枠から離れた治療(自由診療)で行うのかは担当医とご相談して決めて頂ければと思います。
自由診療における根管治療は、その歯の状況に応じて金額が変わります。
ご希望がありましたら、ご相談時に金額はお伝えしております。
根管治療は1歯あたり3回前後で終了することが多いですが、症状次第では治療回数がかかる場合もあります。
治療が終わった後は経過観察を行っていきます。術後3ヶ月・6ヶ月・1年を目安とし、それ以降も継続的な経過観察を行っております。
1回あたり60~90分位の治療時間で行っております。
処置により前後する場合がありますので、その際には事前にお伝えしております。
術前の歯の状況や術後の歯根破折などにより抜歯になってしまう場合もあります。
初回の検査の段階で残存する歯の量が少ない場合は、根管治療後の修復処置や補綴処置が困難になることが考えられますので、抜歯が選択になる場合もございます。
治療中・治療後の不快感を最小限にするために、多くの場合は歯科局所麻酔を行って治療を行っております。
術前に歯科局所麻酔の既往を伺い、使用可能か否かを確認させて頂きます。
根管治療後には被せ物などの修復・補綴処置が必要になります。その処置の精度も根管治療の予後に影響します。
かかりつけ医がいる場合には根管治療のみのご紹介もお受け致します。かかりつけ医がいない場合に関しましては、当院での補綴治療をお勧めしております。
根管治療後には被せ物などの修復・補綴処置が必要になります。その処置の精度も根管治療の予後に影響します。
かかりつけ医がいる場合には根管治療のみのご紹介もお受け致します。かかりつけ医がいない場合に関しましては、当院での補綴治療をお勧めしております。
特殊な事情があるケースに関しましては、
ご紹介いただく前に電話にてご連絡を頂けますと幸いです。
医療法人社団育芯会 理事長 齋藤育実
渡邉浩章
ココロ南行徳歯科クリニック
水、木(第1.3.5週目)、金、土曜日
TEL / FAX .047-314-8841
ハートリーフ歯科クリニック東大島
火、木曜日(第2.4週目)
TEL / FAX .03-6807-0648
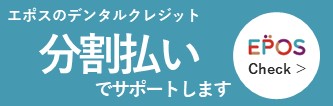
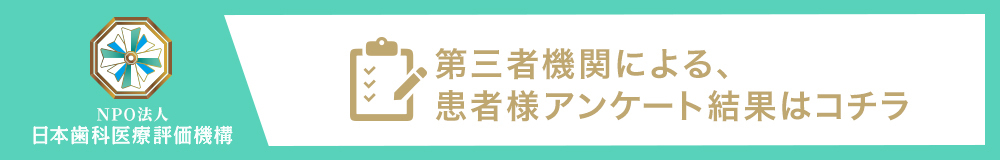

所在地:〒272-0138 千葉県市川市南行徳2丁目20-25ソコラ南行徳店2階207号
tel 047-314-8841
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30 – 19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 土曜、日曜、祝日の診療も行っています
南行徳駅徒歩10分 イオン駐車場680台
問診票ダウンロード PDFファイル